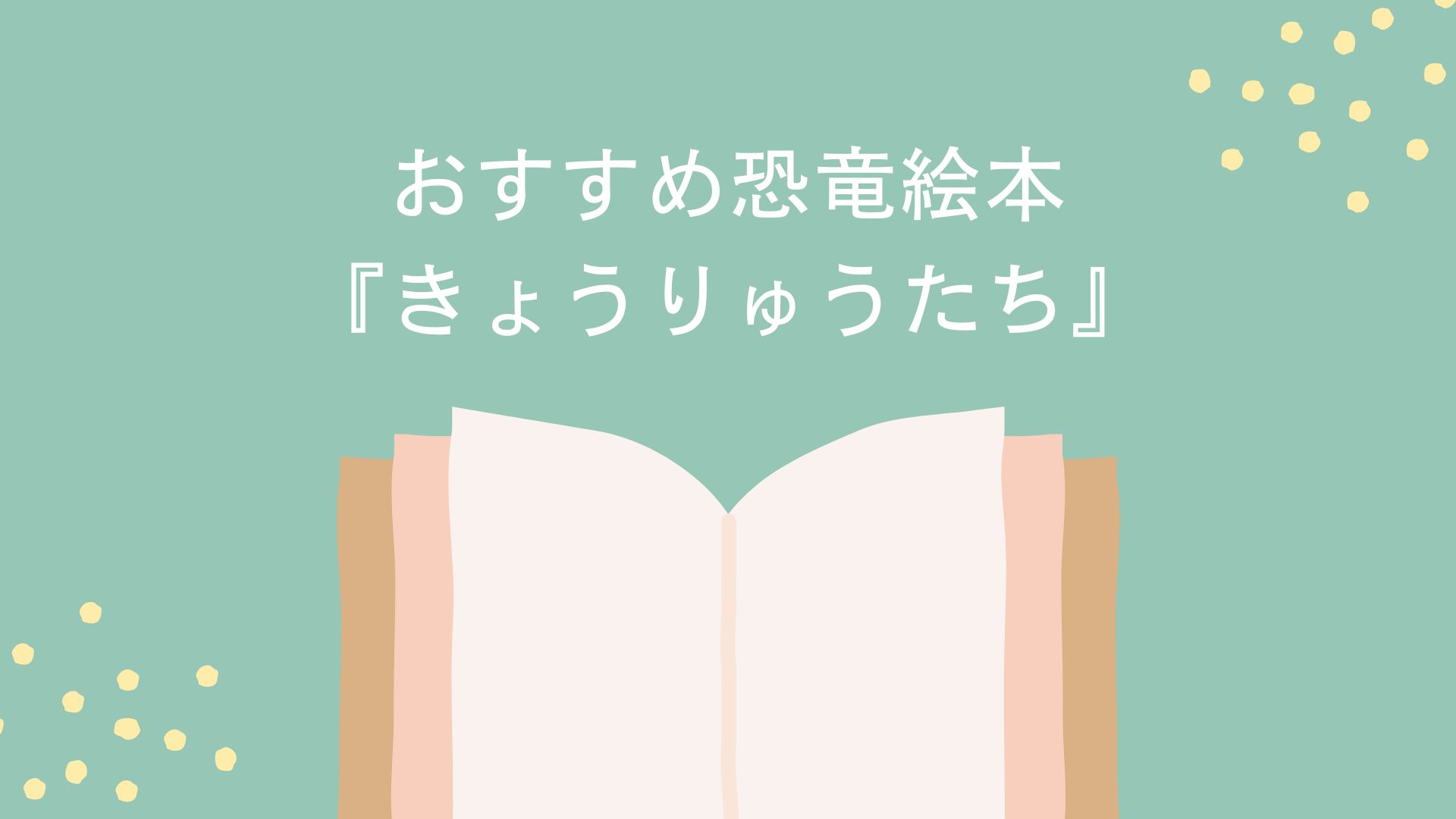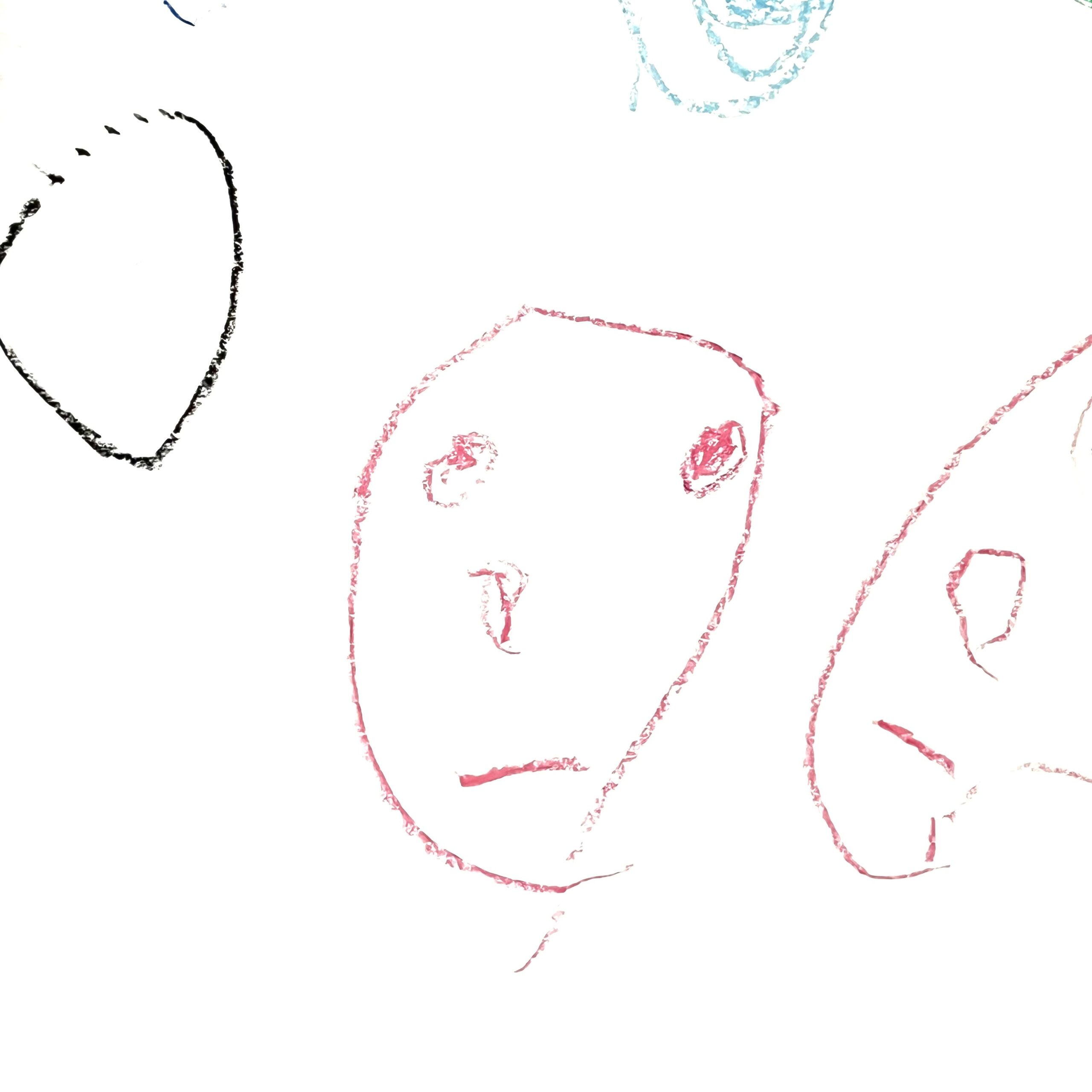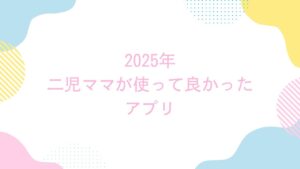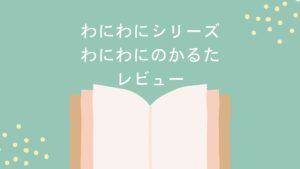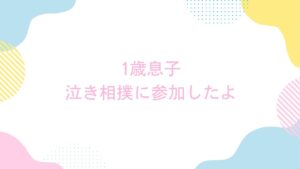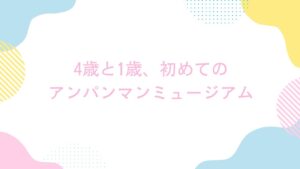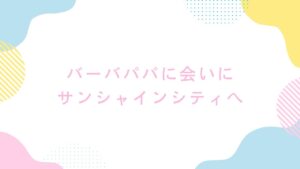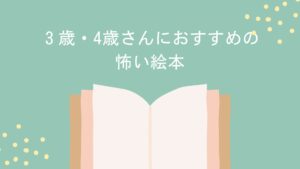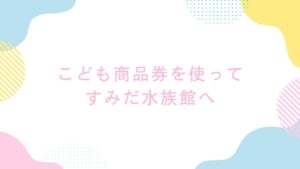うちの子供たち(4歳と1歳)、恐竜が好きなんです。
彼らがハマった恐竜絵本をご紹介します。

『きょうりゅうたち』
きょうりゅうたち
文: ペギー・パリッシュ
絵: アーノルド・ローベル
訳編: 杉浦 宏
出版社: 文化出版局
出版年: 1976年
読み聞かせをした感想
投稿のタイトルに、「子供の心に刺さるおすすめ恐竜絵本」と書きました。
心に刺さる、ということばは、日頃まったく使わないのですが、この絵本を子供たちと一緒に楽しんでいて、心に「響く」、ではなく、心に「刺さる」こそがふさわしい表現だと思ったからです。
優しく穏やかで、あたたかい語り口。でも、説明していることは、ちょっぴり刺激的なのが、この絵本の特徴です。
テラトザウルスは こわい こわい きょうりゅうだったのです。くさを たべる きょうりゅうに おそいかかり、するどい つめで にくを ひきさいて たべて いました。
ペギー・パリッシュ, 1976, 『きょうりゅうたち』, (杉浦宏 訳), 文化出版局.
また、普段読んでいる絵本の多くは、絵がカラフルだけど、『きょうりゅうたち』は、全ての絵において、使われている色の数がとても少ないです。
これが、不思議と子供たちの目を引くようなんですよね。
幼少の頃に初めて読んだ彼の作品が「がまくんとかえるくん」シリーズの中の一つだったので、その印象が強烈に残っているというのもありますが、私にとって、『きょうりゅうたち』の画家であるアーノルド・ローベルの絵のイメージは、「セピア色とオリーブ色の世界」です。
その落ち着いた色合いの絵が、生き生きと、登場人物や動物たちのことを物語ってくれるのです。
私は、がまくんとかえるくんのことが昔も今も大好き。4歳の娘も、初めて読んで以来、何かというとがまくんの口調を真似するくらい、ぞっこんです。
がまくんとかえるくんは、きっと、子供に好かれるオーラを纏っているのでしょう。
『きょうりゅうたち』も、そんな「がまくんとかえるくん」を彷彿とさせる色づかいの一冊。
アーノルド・ローベルの描く恐竜は、ほんとうにリアルで、「ずっしり感」が伝わってきます。
ちなみに、この絵本の中で見逃してほしくないのが、恐竜たちの並ぶ見返しです。
比較対象として載っている象のシルエットが、あまりにもちまっとしているので、恐竜ってこんなに大きかったの?と、改めて驚かされます。
人間と比べて、ではなく、象と比べて、というのが、その巨大さをますます直感的に知らしめてくれていて、絶妙だと感じました。
本文では、とにかく分かりやすく、恐竜たちの大きさや重さ、外観、食べていたものなどについて説明してくれており、子供の頭にもスーッと入っていくようです。
娘は、「ティラノサウルスとアンキロサウルスは、どっちが強かったんだろう?」と、それぞれについて書かれたページを見比べながら呟いていました。
探究心をくすぐられている様子を見て、親として、とても嬉しく思いました。
この絵本のおすすめポイント
すばらしい絵本なので、おすすめポイントはいくつもあるのですが、その中から三つ挙げます。
11種類の恐竜が紹介されている
この絵本では、11種類の恐竜について著述されています。
ステゴザウルス
ディプロドクス
アンキロサウルス
ブロントザウルス
コンプソグナトス
テラトザウルス
アナトザウルス
オルニトミムス
ブラキオザウルス
ペンタセラトプス
ティラノザウルス
※恐竜の名称は本文の表記に倣いました
きっと、お気に入りの恐竜が見つかることでしょう。
4歳の娘はティラノサウルスが好きなのですが、この本を読んで、テラトザウルスも好きになりました。後ろ足でニョキッと立っている様子が面白いらしいです。
1歳の息子は、コンプソグナトスが赤ちゃん恐竜に見えるそうで、「かわいい!」と、大興奮でした。
拾い読みもできる
読んであげるなら4歳から、と記載されていますが、いざページをめくってみると文字がぎっしりで、大丈夫かな?と感じる方もいるかもしれません。
でも、大丈夫。大きめの文字と小さめの文字の部分があり、拾い読みがしやすい構成になっています。
私の場合は、1歳の息子へ読み聞かせるときは、恐竜のページのみとか、適宜省略しながらとか、大きめの文字だけとか、調整して読んでいます。
文章にロマンが感じられる
きょうりゅうたちは ながい あいだ この ちきゅうの うえの どこにでも すんでいました。けれども とおい むかしに しにたえてしまいました。どうして しにたえてしまったか、その わけは ほんとうには だれも しりません。けれど、ともかく この ちきゅうじょうに ただ いちど きょうりゅうたちの せかいが あったのです。
ペギー・パリッシュ, 1976, 『きょうりゅうたち』, (杉浦宏 訳), 文化出版局.
この部分に、私は痺れました。
なんて、途方もない時の流れと、恐竜たちが確かに存在していた事実とを感じさせてくれる文章だろうか。
人類の誰一人として、見たことのない恐竜。それでも、人々が研究してきた結果、いま、この世の中には、恐竜関係の施設、映像、図鑑、書籍、いろいろなものが溢れていて、誰もが容易にその生態を目の当たりにすることができます。
これは、時の流れという、何者も太刀打ちできないと思われていたものを、研究者たちが乗り越えてきたということに、他ならないのではないでしょうか。
乗り越えるパワーの源は、やはり、太古の昔に思いを馳せるときに感じる「ロマン」かもしれない。そういったことを、しみじみと思わせてくれる絵本です。
子供たちの年齢が上がるにつれ、この作品の文章の素晴らしさを噛みしめてくれるようになることを期待しています。
著者・画家・翻訳者について
〈作〉ペギー・パリッシュ
1927年、アメリカ・サウスカロライナ州に生まれる。サウスカロライナ大学を卒業後、教師としてオクラホマ、ケンタッキーの学校で働く。ニューヨークのドルトンスクールでは15年以上に渡り教鞭を取った。 約30冊の児童書を世に送り出し、「AMELIA BEDELIA (アメリア・バデリア)」のシリーズが特に有名で、広く親しまれている。他の著書に『うさぎがいっぱい』など。1988年、サウスカロライナにて他界。
〈絵〉アーノルド・ローベル
1933年、アメリカ・ロサンゼルスに生まれる。高校卒業後に入学したブルックリンのプラット・インスティテュートにて本のイラストレーションを学ぶ。妻で絵本作家のアニタ・ローベルとは、互いに影響を与えあいながらそれぞれの作品を世に送り出し続け、『わたしの庭のバラの花』など、アーノルドが文、アニタが作画を担当した絵本も出版された。『ふたりは ともだち』(コルデコット賞次賞・全米図書賞)に始まる「がまくんとかえるくん」シリーズ等、彼の著書は世界中で愛読されている。『ローベルおじさんのどうぶつものがたり』でコルデコット賞など、受賞多数。その他の作品に『どろんこ こぶた』『ふくろうくん』『おはなし ばんざい』などがある。1987年、ニューヨークで他界。
〈訳編〉杉浦 宏
1930年、東京生まれ。日本大学農学部水産学科卒業後、上野動物園水族館、井の頭水生文化園、上野動物園飼育課での勤務を経て、国際学院埼玉短期大学教授を務めた。専攻は魚類学、生態・環境学。ラジオ番組「全国子ども電話相談室」の回答者としても活動した。水にすむ生き物についての子供向けの本を始め、多くの著書がある。