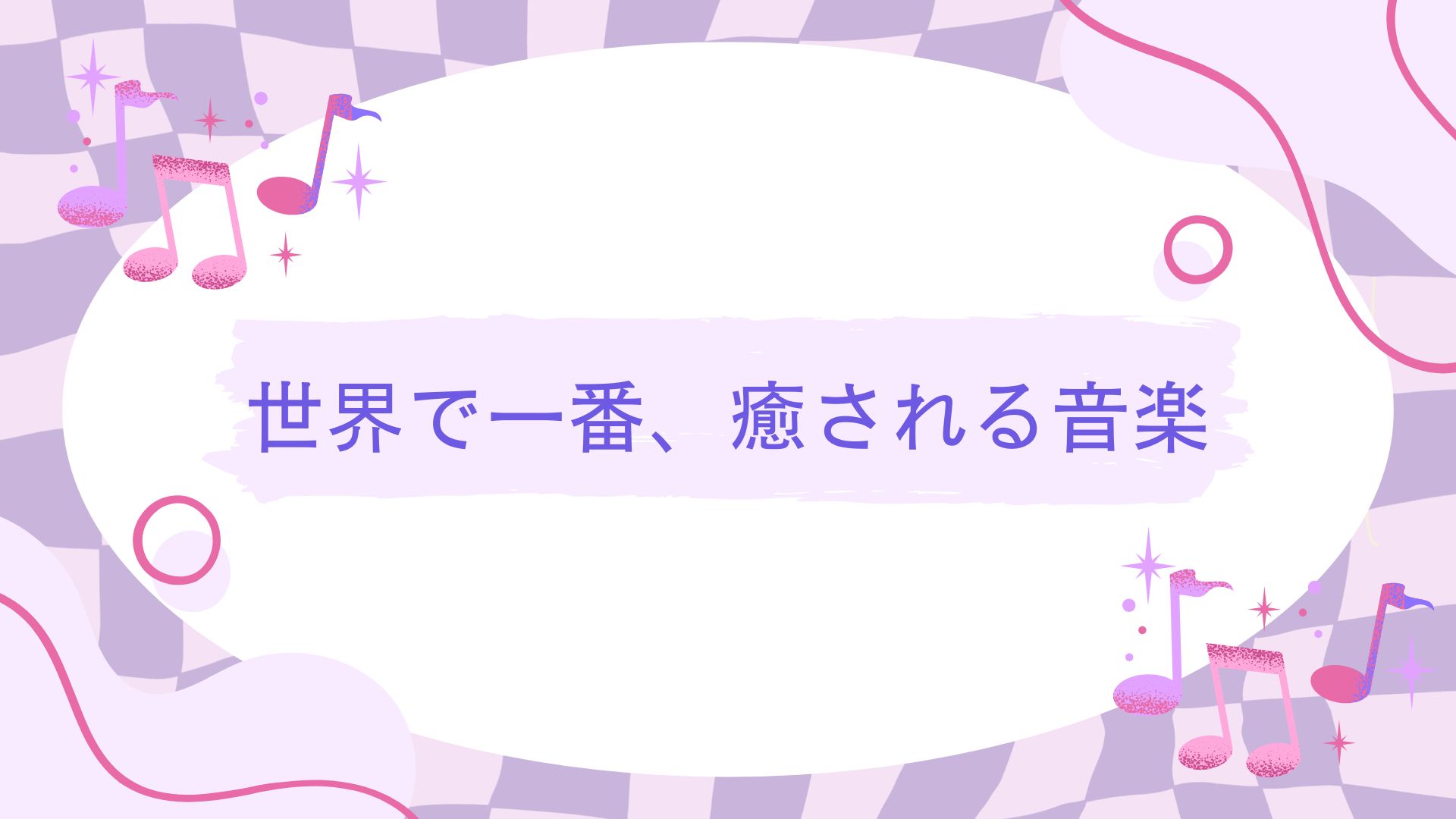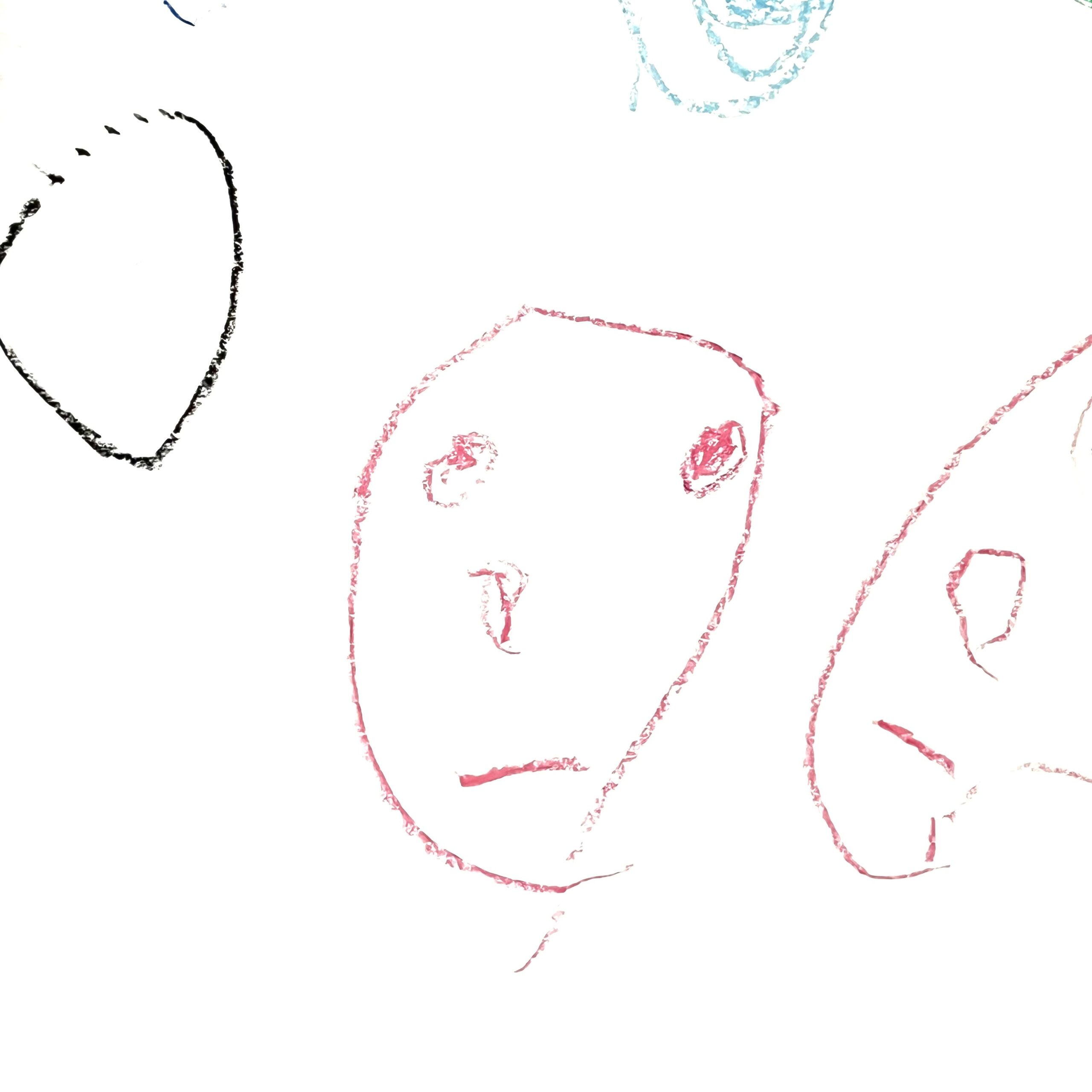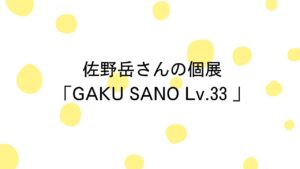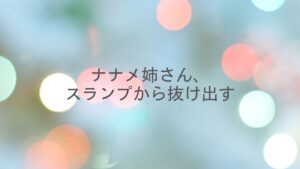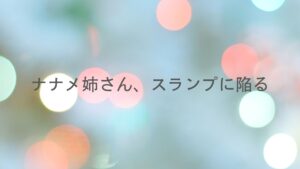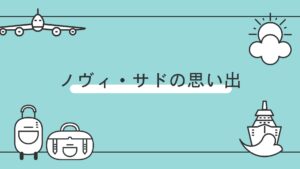日々生活していると、癒されたくて仕方ないと思う瞬間が否応なしにやってくるのですが、いま現在この世の中に存在する音楽の中で、一番自分を癒してくれる音楽について、書きたいと思います。
癒しの音楽、ブルッフ作曲《ロマンス》
表題にもあるように、その音楽とは、こちらの作品のことです。
マックス・ブルッフ作曲《ロマンス ヘ長調 作品85 》
ヴィオラと管弦楽のための作品で、1911年に書かれました。
作曲家ブルッフについて
マックス・ブルッフ Max Bruch(1838−1920)
ドイツの作曲家・指揮者。
出版されている作品数は約200曲。特に有名な作品に《ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調》があります。彼は、音楽はメロディックで親しみやすいものであるべきだ、という信念を持っていました。
音楽スタイルが変化していった時代を生きた作曲家でしたが、「ロマン派 (19世紀の抒情的な音楽)」に終生、忠実であり続けました。
《ロマンス》という作品について
もともとはラテン語に由来するロマン語、ロマンス語による文学を意味する言葉だった「ロマンス」は、フランスとドイツでは18世紀に現れ、感傷的な性格の詩と音楽形式を意味するようになったそうです。多くの作曲家が緩徐楽章や小品としてロマンスと銘打った楽曲を書くようになり、抒情的な器楽曲のジャンルの一つとなりました。
ブルッフの作曲した《ロマンス ヘ長調 作品85》も、例に漏れずたいへん抒情的、かつメロディアスな一曲。
冒頭の旋律から、ブルッフの音楽の世界に引き込まれます。ヴィオラとオーケストラが織りなす切なさに満ちたハーモニーも、心をとらえて離しません。中盤の激情を思わせる盛り上がりも、聴きどころの一つでしょう。
ヴィオラ・ソロの曲が書かれることが滅多になかった時代に生まれた、ヴィオラが主役の作品です。
この作品を聴いて思うこと
「愛」の音楽だな、という印象を受けます。
音楽辞典とCDのブックレット以外に、作曲家ブルッフについて著述されたものをあまり見つけることができないため(数々の傑作を世に送り出した音楽家にも関わらず、なのです)この作品が生まれた経緯について、細かいバックグラウンドは分かりません。
ただ、私自身は、
穏やかな眼差し、叶わぬ想い、輝かしい景色、高揚感あふれる喜び、渦巻く不安、届かぬ言葉、やさしさに満ちた会話。
そういったものたちを音楽から感じ取りました。
これほどの傑作を書き上げた時、ブルッフは何を思ったんだろう。
「自分は、とんでもないモノを生み出してしまった…!」って震えてもおかしくないんじゃないだろうか。
いつ聴いても、音楽っていいな、クラシックっていいな、そう思わせてくれるのが《ロマンス ヘ長調 作品85 》なのです。
ブルッフ作曲《ロマンス》との出会い
私は、ピアノの演奏と指導を生業としています。
西洋の伝統音楽であるクラシック音楽には、小学校に上がる前からから親しんできました。

ただ、ピアノの練習に励んでいると、どうしても、クラシック音楽の中の「ピアノ・ソロの曲」または「ピアノと何かが共演する曲」に知識が偏っていっていたように思います。
自分にとって〈究極に癒される音楽〉と出会った時には、ピアノを始めてから実に13年半という月日が経過していたのでした。
当時、18歳。音楽大学に通っていた私は、友人たちと自主企画でコンサートを開催することになりました。
メンバーは、ヴァイオリン2名、ヴィオラ1名、チェロ1名、ピアノ2名。
コンサートの第一部は、それぞれのメンバーがソロを1曲ずつ弾き(弦楽器はピアノ伴奏あり)、第二部はピアノ五重奏、という構成で、ヴァイオリンの友人の伴奏と自分のソロを終えた私は、次の出番に備え、休息を取っていました。


すると、ステージのほうから、あの甘美なメロディーが聴こえてきたのです。
甘美な、という形容動詞は、日頃まったく使う機会がない言葉です。私にとっては。
が、あのとき聴こえてきたのは、甘美なメロディー、としか言い表すことができませんでした。
私は急いでプログラムを確認しました。
胸を打つこの曲は一体何なのだろう、誰が作曲したのだろう。
これが、私と、ブルッフ作曲《ロマンス》との出会いです。
ブルッフ作曲《ロマンス》の名演
コンサートの時は、《ロマンス》はヴィオラとピアノのデュオによって演奏されていましたが、後から調べてみると、原曲は、ヴィオラと管弦楽のための作品だということが分かりました。
あの甘美な旋律の魅力に囚われてしまった私は、色々なCDを聴き漁りました。
息を呑むほどに正確な音程の、美しい演奏。抑えた表現がクールな、渋い演奏。強弱の幅が広く自由自在で、立体的な演奏。沢山の素晴らしい録音があり、愛聴していました。
そして、つい昨年のこと。こちらの録音に巡り逢ったのです。
ユーリ・バシュメット (ヴィオラ)
ロンドン交響楽団
ネーメ・ヤルヴィ (指揮)
【Bruch, Walton, Yuri Bashmet, L Double Concerto / Viola Concerto(1990年発売)】より





サブスク、万歳(涙)。
この名録音を知ることができたのは、Apple Music のお陰です。
どうかどうか、一人でも多くの方に聴いてほしい。
初めて聴いた時は、涙腺崩壊状態でした。
大好きで大好きで仕方ない、何年も恋焦がれ続けてきたあの甘美な旋律が、かつてないほどの優しい、温かい音で、耳から流れ込んでくる。
ヴィオラって、いや、弦楽器って、こんな風に鳴らすことができるの?
尖ったところが一個もない。それでいて、どの演奏よりも力強い。あの細い弦に全体重が無理なく乗っかっている、そんな豊かな響きがする。
ヴィブラートが切なく美しい。しかも色んな場面で全く種類の違う切なさを味合わせてくれる。
トリルの巧さに度肝を抜かれる。心を躍らせる、聴き手を音楽の中に引っ張り込むようなトリル。
ディミヌエンドの絶妙さに心を打たれる。ダイナミクスの幅がすごい。どれほど弱い音になっても、そこに「歌」と「魂」がある。
オーケストラも素晴らしい。果てなき空間を感じさせる、広がりのあるトゥッティ(合奏)。
しかも、この曲で、これほどまでにヴィオラにぴったりと沿うようなオーケストラは、今まで聴いたことがなかった。
この演奏全体の完璧なバランスは、いったいどうしたら生まれるのだろう。
音が減衰していく鍵盤楽器であるピアノ一台では、こういった表現は、絶対にできない。羨ましいくらいに異次元の音楽が繰り広げられている。でも、本当に、ピアノではこういった演奏はできないのだろうか…?
この世で一番、私を癒してくれる音楽が、ピアノ・ソロの曲ではなくて、ピアノと何かが共演する曲でもなくて、ヴィオラと管弦楽のための曲である理由の一つが、ここにあるのかもしれません。


自分が一生演奏することの叶わないであろう楽器。それらが奏でる至高の音。
ピアノで何とか表現できないだろうか、と追い求めてしまう随一の芸術が、この作品にはある。そう感じるのです。
私はきっと、いつまでもいつまでも、この曲に憧れを抱き続け心を震わされ、そして、涙を流し、癒しを与えてもらうのでしょう。
演奏者について|ユーリ・バシュメット(ヴィオラ)
1953年生まれ。ロシア出身のヴィオラ奏者、指揮者。ヴィオラがソロ楽器としても世間に浸透するに至ったのは、彼による功績が大きいと言われています。各国で演奏ツアーを行い、ソリストとして世界の名だたるオーケストラとの共演を重ねる傍ら、室内楽の分野でも活躍してきました。1992年に合奏団「モスクワ・ソロイスツ」結成。バシュメット自身が指揮をして各地で公演を行っています。
演奏者について|ネーメ・ヤルヴィ(指揮)
1937年生まれ。世界各国の一流オーケストラの首席指揮者・音楽監督を歴任し、数多くの賞・名誉博士号を授与されている、エストニア出身の指揮者。これまでに最も多くの録音をしている指揮者の一人でもあり、あまりメジャーではない作品も多く取り上げ、世に広めています。
演奏者について|ロンドン交響楽団
1904年に設立された、イギリスが誇るオーケストラ。世界各国で公演を行っています。映画音楽の録音にも数多く取り組んでおり、『スター・ウォーズシリーズ』が特に有名です。
本当は、語り尽くしたい
世界で一番自分を癒してくれる音楽について、書かせていただきました。
本当は、



何小節目の何拍目のあの和音、翳りが感じられてたまらないんだよね



オーボエ、弦楽器、ヴィオラのソロ、とメロディーが重なっていくところがエモいんだよね
などと、譜例を貼り付けた上で語り尽くしたいです。
なぜなら私は、変態的なクラシック音楽好きなので。
でも、それをしていたら、あまりにも記事が長くなってしまうし、音楽の専門用語を、音楽をやっていない方々に分かりやすくお伝えする文章力が自分にはまだまだ足りないな、と思ったのです。
だから、またいつか語らせていただきたいと思います。
それだけ、ブルッフの《ロマンス ヘ長調 作品85 》には、人を惹きつけてやまない魅力があるのですよ。