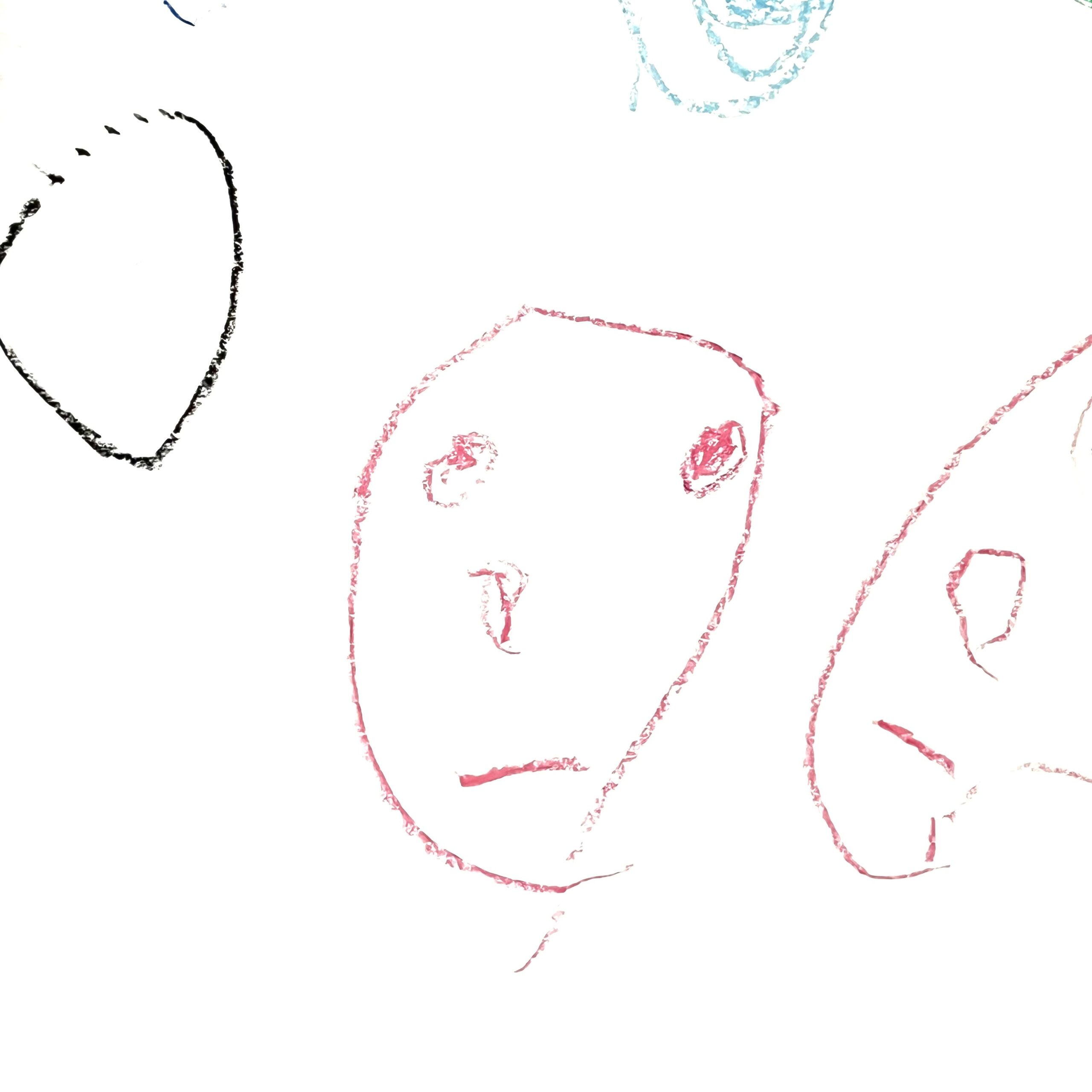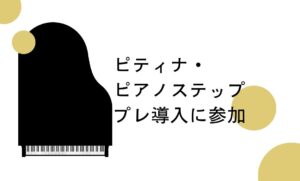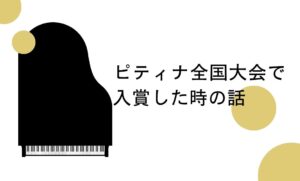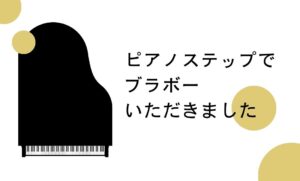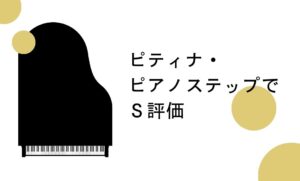第19回ショパン国際ピアノコンクール本選の様子をYouTubeで視聴しました。
ライブ配信で聴けた方とそうではない方がいますが、とにかく、本選に残った11人のピアニスト全員の演奏を結果発表前に聴き終わりました。
感想を書いていきます。
Tianyou LI (中国)
どんなコンクールでも、初日のトップバッターって、一番大変だと思うのです。コンクールで絶対にトップバッターで弾きたい!と考えるコンテスタントはいないはず。
そんな重圧を乗り越えて、ものすごい集中力でもって一音一音が紡がれた1曲目、幻想ポロネーズ。柔らかく伸びのある音と、「ホール全体を鳴らしている」かのような豊かな響きに感銘を受けました。
協奏曲では、オケに耳を澄ませつつ、自分の鳴らす音と、この共演を楽しんでいる様子が、ビシビシ伝わってきました。
奇をてらったところのない、温かみに満ちた演奏だったと思います。
とても好感を持って受け入れられるタイプの演奏家なのではないでしょうか。
Eric LU (アメリカ)
なんという憂いに満ちた美しい出だしでしょう。決して声を張り上げることなく、切々と訴えかけてくる幻想ポロネーズ。
それでいて音の一つ一つにずっしりとした重みがあり、会場でその響きを是非とも体感したいと思わされました。
協奏曲は、演奏するコンテスタントが毎回少ない第2番を選択。この作品の新たな魅力を目の当たりにした思いです。
私は、フィギュアスケーターのミシェル・クワンが大好きなのですが、選手時代の彼女の名演技をふと思い出したのでした。風格ただよい、根底にあるスケートへのひたすらな愛が感じられるスケーティング。
エリック・ルーの場合は、ピアノへの並々ならぬ愛が、画面からこれでもかと溢れているように思えてならなかったのです。
Tianyao LYU (中国)
1曲目の幻想ポロネーズで、何と堂々とした演奏家だろう、という印象を受けました。
協奏曲では、爽やかでみずみずしいショパンを聴くことができました。こんな演奏を聴きたいと思っていた聴衆は多いのではないでしょうか。一つ一つのフレーズの歌わせ方が粋だな、と感嘆するばかりです。
軽快なテンポに乗って駆け抜けた第3楽章では、コーダへ向けて会場のボルテージが徐々に上がっていく様子が見てとれたような気がしました。
華があり、聴く人の心を掴むピアニストですね。
Vincent ONG (マレーシア)
彼の演奏について書こうとしても、何をどう書けば良いのか、初めはさっぱり分からず、文章もまとまりませんでした。
異次元のピアノを聴き、呆然とするほどに衝撃を受けたのです。
鍵盤打楽器であるピアノ、一度打鍵したら音が減衰するはずのピアノが、自由自在に歌っている。
楽曲の解釈がとにかく新鮮。そのパッセージをペダル無しで弾くの?そこをノンレガートで弾くの?驚きでいっぱいです。
ハーモニーとメロディーの、理想的なバランスにも出会えた気がしました。
1曲目の幻想ポロネーズで彼の音楽に驚愕し、協奏曲が終わらないうちに「もっと彼の演奏をたくさん聴きたい」と思っていました。そして実際、その日のうちに予選の演奏も動画で視聴しました。
素晴らしい音楽家の存在を知ることができて、幸福に思っています。
進藤実優 (日本)
タッチがとてもしっかりしていて芯のある音で、幻想ポロネーズでは、そんな彼女ならではの音色で聴衆を音楽の世界に引き込んでいるな、と感じました。
協奏曲では、ピアノ対オーケストラ、と分離を感じさせるのではなく、時にはオケに溶け込み、また時には寄り添い、まるで何度も共に練習を重ねた仲間と室内楽を奏でているかのように聴こえる瞬間が多々ありました。
この「オーケストラとの調和」は、彼女が演奏に没頭しつつもホール全体に響き渡る音を冷静に捉えているからこそ、そして、柔らかなハーモニーや豊潤なバスを繰り出す素晴らしい左手の技術持っているからこそ、成せる技なのでしょう。
3楽章が始まった途端、光の中の雨粒を思わせる軽やかでパラパラとした音色に。ハッとさせられる変化でした。
心地よい流れ、どこまでも端正な音楽、ブラボーでした。
Zitong WANG (中国)
この楽器って、こんなに優しく柔らかい音が出せるんだ…と、シゲルカワイの魅力を改めて知ることとなった幻想ポロネーズでした。
協奏曲では一転して、圧倒されるほどにズドーンと重みのある音。
それでも決してきつくなることはなく、自身の内面と向き合うごとく静謐な雰囲気をたたえた出だしでした。
短調の音楽っていいな、としみじみと思わされた、切なさに満ちた第1楽章。まろやかな音質の第2楽章。こちらの心まで浮き立ってくる軽快な第3楽章。それぞれがそれぞれに印象的で、かつ、うちに秘めた炎のような情熱が伝わってくる演奏だったように思います。
William YANG (アメリカ)
すっきりとクリアで、清涼感のある音。
舞台上でスタンウェイを演奏した時に、私自身はハンマーが弦を叩く音を感じるのですが、不思議と、テレビ画面を通して彼の演奏からそれを感じるような気がしました。
生演奏ではないのに、動画なのに、これほどまでに臨場感を味わうことができるとは。
技術的な危うさが皆無で安定感が抜群でした。1曲目の幻想ポロネーズで、ああ、何と安心して身を委ねられる音楽だろう、と、コンクールの本選の演奏を聴いているときにおよそ思ったことのないような感想を抱いたほどです。
音楽のフレーズを大きく捉え、協奏曲では、ぐいぐいとオケを引っ張っていっている様子が見られ、若くして「大家(たいか)」の雰囲気を漂わせた演奏家だ、という印象が強く残りました。
Piotr ALEXEWICZ (ポーランド)
柔らかく、重厚感のある音質。幻想ポロネーズでは、ここの音楽はこんな風に進むのかな、と思いきや瞬間的にサッと翻って意外性のある音色を聴けたり、ということの多い、とてもチャーミングで興味深い演奏でした。
拍の刻み通りではなく、ほんの少しずらして鳴らしたりしている時があるのですが、ああ、ヨーロッパの演奏だな…と、とても好感を持って聴くことができました。
特筆すべきは、協奏曲第2番の第2楽章。丸くてあたたかな音はどこまでも優しく、涙をさそうメロディーを一層引き立たせていました。
Kevin CHEN (カナダ)
力強くありつつも、均衡のとれた幻想ポロネーズ。弾むような音で、聴いている側がパワーをもらってしまうような、活力に満ちた協奏曲。
会場では一体どのように響いているのだろう、と知りたくなる、信じられないほどの強靭なタッチでした。
人間の一本一本の指で打鍵されているはずの音が、太く太く、どこまでも重厚な響きで、倍音をともなって会場の一人一人に届いている様子が想像されます。
彼の演奏の感想を文章にしようとすると、余裕、笑顔、パーフェクト、快活、歯切れの良さ、エネルギッシュ…、幾つもの単語が浮かんでくるのでした。
時にものすごいスピードになることがあっても、あくまでその安定感が崩れない演奏は、見事としか言いようがありません。
David KHRIKULI (ジョージア)
ショパンの響きが、音の帯が、聴く人を包み込む。そういった感覚を覚える幻想ポロネーズでした。
音質は硬質で、高音がきらめきます。重低音の和音は鍵盤の下まで突き抜けるようなタッチで、迫力が伝わってきました。
協奏曲は、テンポに乗って飄々と進んでいく、と思わせて、実のところこの上なく繊細でロマンチック、という名演だったように思います。
フレーズの終わりをあれほど優しく弾くことができるなんて、彼の(美しいものを美しいと感じる・とらえる)感性の鋭敏さを感じました。
桑原志織 (日本)
暗く、情念のこもった幻想ポロネーズの出だし。
それはやがて音楽ホール全体を巻き込むような情熱に満ちた音の渦となり、聴衆の心の高揚が、画面の向こうの一視聴者にすぎない自分にさえ、はっきりと伝播してきたのでした。
協奏曲では、音質がパッと明瞭に。雄大な流れにのって奏でられるメロディーは、切なく奏でられます。
しかし、その切なかった音楽に、いつの間にか希望の光が差し込んでくるのです。演奏の構成力の妙というものを堪能できました。
彼女ならではの音色というものがあり、彼女にしか成しえない世界観が終始一貫しており、崇高なステージを見させてもらったという思いでいっぱいです。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4539b47c.ffab8bd3.4539b47d.f0038534/?me_id=1213310&item_id=21711979&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3801%2F9784276963801_1_31.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4539b47c.ffab8bd3.4539b47d.f0038534/?me_id=1213310&item_id=20769587&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2341%2F9784087212341_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)